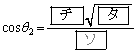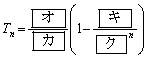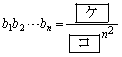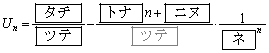�@�Z���^�[�������wIIB 2009�N���@
�y�L���z��������L���ł��B�����̊F���܂̂��x�������������肽���A��낵�����肢�������܂��B
�y�L���z�L���͂����܂łł��B
[1][1]�@ �C
�C �C
�C �̂Ƃ��A
�̂Ƃ��A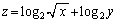 �̍ő�l�����߂悤�B
�̍ő�l�����߂悤�B
 �C
�C �Ƃ����ƁAs�Ct�C
�Ƃ����ƁAs�Ct�C �̂Ƃ蓾��l�͈̔͂͂��ꂼ��
�̂Ƃ蓾��l�͈̔͂͂��ꂼ���ƂȂ�B�܂�
�����藧����Az�� �C
�C �̂Ƃ��ő�l
�̂Ƃ��ő�l ���Ƃ�B���������āAz��
���Ƃ�B���������āAz�� �C
�C �̂Ƃ��ő�l
�̂Ƃ��ő�l ���Ƃ�B
���Ƃ�B [2]�@ �͈̔͂�
�͈̔͂� 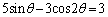 �@���(��)
�@���(��)����θ �ɂ��čl���悤�B
������(��)�� ��p���ĕ\����
��p���ĕ\���� �ƂȂ�B���������āA ���
��� �ł���A �͈̔͂ł��̓�������θ �̂����A����������
�͈̔͂ł��̓�������θ �̂����A���������� �C�傫������
�C�傫������ �Ƃ����
�Ƃ���� 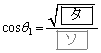 �C
�C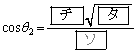
�ł���B
 �ɂ��ĕs����
�ɂ��ĕs���� �����藧�B
�����藧�B �ɓ��Ă͂܂���̂��A����
�ɓ��Ă͂܂���̂��A���� �`
�` �̂��������I�ׁB
�̂��������I�ׁB
 �@
�@
 �@
�@


 �@
�@
 �@
�@
 �������A�K�v�Ȃ�A���̒l
�������A�K�v�Ȃ�A���̒l  �C
�C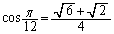
��p���Ă��悢�B
����ɁA�s���� �������R��n�̂����ŏ��̂��̂�
�������R��n�̂����ŏ��̂��̂� �ł���B
�ł���B [��]
[2]�@������ ��C�C�_
��C�C�_ ��A�Ƃ���B
��A�Ƃ���B
�_Q �Ɋւ��āA�_A�ƑΏ̂ȓ_��P
�Ɋւ��āA�_A�ƑΏ̂ȓ_��P �Ƃ���ƁA
�Ƃ���ƁA
 �C
�C
�ł���B
��̕�����C��D�̌�_��R��S�Ƃ���B�������Ax���W�̏���������R�Ƃ���B�_R�CS��x���W�͂��ꂼ�� �C
�C �ŁA�_R�CS�ɂ����������D�̐ڐ��̕������͂��ꂼ��
�ŁA�_R�CS�ɂ����������D�̐ڐ��̕������͂��ꂼ��
 �C
�C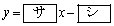
P�������D��̓_�Ƃ��AP��x���W��a�Ƃ����BP����x���Ɉ����������ƕ�����C�Ƃ̌�_��H�Ƃ���B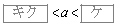 �̂Ƃ��A�O�p�`PHR�̖ʐ�
�̂Ƃ��A�O�p�`PHR�̖ʐ� ��
��
�ƕ\�����B ��
�� �̂Ƃ��A�ő�l���Ƃ�B
�̂Ƃ��A�ő�l���Ƃ�B
 �̂Ƃ��A����HR�ƕ�����D�̌�_�̂����AR�ƈقȂ�_��x���W��
�̂Ƃ��A����HR�ƕ�����D�̌�_�̂����AR�ƈقȂ�_��x���W�� �ł���B���̂Ƃ��A
�ł���B���̂Ƃ��A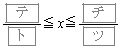 �͈̔͂ŁA������D�ƒ���PH����ђ���HR�ň͂܂ꂽ�}�`�̖ʐς�
�͈̔͂ŁA������D�ƒ���PH����ђ���HR�ň͂܂ꂽ�}�`�̖ʐς� �ł���B
�ł���B
[��]
[3]�@ ������
������ ��1�Ō��䂪
��1�Ō��䂪 �̓��䐔��Ƃ���B����
�̓��䐔��Ƃ���B���� �̋����Ԗڂ̍������o���āA����
�̋����Ԗڂ̍������o���āA���� ��
�� (
( )�Œ�߂�B
)�Œ�߂�B �Ƃ����B
�Ƃ����B
(1)  �����䐔��ł���A���̏�����
�����䐔��ł���A���̏����� �C����
�C���� �ł���B
�ł���B ����������
�ł���B�܂��A�� �����߂��
�����߂�� �ƂȂ�B
(2) ���ɁA���� ��
�� (
( )�Œ�߁A
)�Œ�߁A �Ƃ����B
�Ƃ����B 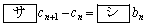 �@(
�@( )
)�����藧����
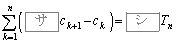 �@����@
�@����@�ł���B�܂��A���̍��ӂ̘a���܂Ƃߒ����ƁA �C
�C �C
�C ��p����
��p���� 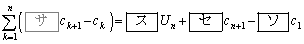 �@����A
�@����A�ƕ\�����B
�@�ƇA���
�ƂȂ�B
[��]
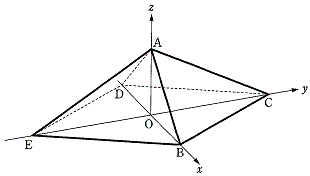 [4]�@O�����_�Ƃ�����W��Ԃɂ�����5�_��A
[4]�@O�����_�Ƃ�����W��Ԃɂ�����5�_��A �CB
�CB �CC
�CC �CD
�CD �CE
�CE �Ƃ���B�Ђ��`BCDE���ʂƂ���l�p��A-BCDE�ƁA����ABC�ɕ��s�ȕ��ʂƂ̋��ʕ����ɂ��čl����B
�Ƃ���B�Ђ��`BCDE���ʂƂ���l�p��A-BCDE�ƁA����ABC�ɕ��s�ȕ��ʂƂ̋��ʕ����ɂ��čl����B
(1)  �ł���A�O�p�`ABC�̖ʐς�
�ł���A�O�p�`ABC�̖ʐς� �ł���B
�ł���B (2)  �C
�C �Ƃ����B
�Ƃ����B �Ƃ��A�_
�Ƃ��A�_ �����BE��a�F
�����BE��a�F �ɓ�������_�Ƃ���ƁA
�ɓ�������_�Ƃ���ƁA �ł���B�_
�ł���B�_ ��
�� �Œ�߁A���� �Ɛ���AE������邱�Ƃ��������B
�Ɛ���AE������邱�Ƃ��������B ��̓_P�́A
��̓_P�́A ����b��p����
����b��p���� �ƕ\�����B�܂��AAE��̓_Q�́A ����c��p����
����c��p���� �ƕ\�����BP��Q��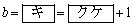 �̂Ƃ���v���邩��A����
�̂Ƃ���v���邩��A���� ��AE�́AAE��
��AE�́AAE�� �F
�F �ɓ�������_�Ō���邱�Ƃ��킩��B���̓_��
�ɓ�������_�Ō���邱�Ƃ��킩��B���̓_�� �Ƃ���B
�Ƃ���B
�_ ��
�� �Œ�߂�ƁA���l�ɍl���邱�Ƃɂ��A���� �Ɛ���AD���AAD��
�Ɛ���AD���AAD�� �F
�F �ɓ�������_�Ō���邱�Ƃ��킩��B���̓_��
�ɓ�������_�Ō���邱�Ƃ��킩��B���̓_�� �Ƃ����
�Ƃ���� �ł���A�O�p�` �͎O�p�`ABC�ƕ��s�ł��邩��A�l�p�`
�͎O�p�`ABC�ƕ��s�ł��邩��A�l�p�` �̖ʐς�
�̖ʐς� �ł���B
�܂�
[��]
�y�L���z��������L���ł��B�����̊F���܂̂��x�������������肽���A��낵�����肢�������܂��B
�y�L���z�L���͂����܂łł��B
�@�@���wTOP�@�@TOP�y�[�W�ɖ߂�
�y�L���z��������L���ł��B�����̊F���܂̂��x�������������肽���A��낵�����肢�������܂��B
�y�L���z�L���͂����܂łł��B
�e���̒��쌠��
�o���w�ɑ����܂��B©2005-2024(�L)����� ��w�y�w�m ���������t���I���n��w�l�b�g�m��w�y�w�m(���ē���������)������́A
�܂��A������܂Ń��[����
�����肭�������B 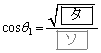 �C
�C